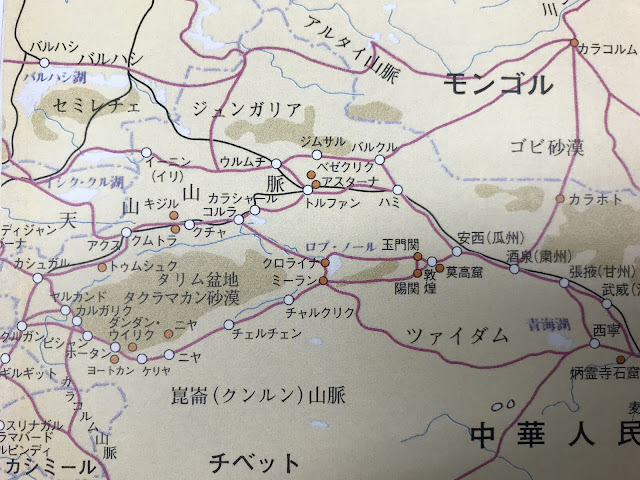シルクロードのものがたり(48)
玉(ぎょく)とはいったい何なのか?
三光汽船のシンガポール駐在員の頃は、マレーシア・インドネシア・タイ・香港が守備範囲だったので、この方面には頻繁に出張していた。出張というと聞こえがいいが、日本からの荷主・現地での受け荷主・代理店の方々と一緒に本船を訪問したり、食事やゴルフをしたり、時には彼らと一緒に1-2泊で旅行をすることもあった。
日本郵船・商船三井を含め海運会社の駐在員は、お客様との信頼関係を築くのが仕事のメインで、事務的な仕事はローカルスタッフにまかせ、自分ではほとんどしない。だから、船会社以外の商社や銀行などの駐在員からは、「船会社の人っていつも遊んでいるみたいだね」とよく言われていた。
各地をウロウロと旅をしていて、これらの国に住む中国系の人々の指輪の「へんてこな石」が気になって仕方なかった。ダイヤモンドやルビーなどの宝石ではない。ただの石っころを、嬉しそうに指輪にしているのだ。
二度・三度食事を一緒しているうちに心やすい関係になる。「その指輪の石、いったい何なの?」と聞いてみる。「これは石ではないよ。玉(ぎょく)なんだ。ルビーやサファイヤより値段が高いんだぜ」と口をとがらせる。そして、この玉なるものがどれほど貴く自分の身の安全を守ってくれるかを、長時間とうとうと弁じる。何人もの人が、同じように得意げに説明してくれた。「石に対する一種の信仰だな」と私は思った。
今回シルクロードに関する本を読んでいて、この玉に対する中国人の愛着・信仰の歴史は、私が考えていた以上に古いものだということがわかった。当初は3500年ほど昔の殷の時代がその起源かと考えていたのだが、どうももっと古いらしい。
「8000年前の新石器時代の興隆窪(こうりゅうわ)文化の遺跡から玉器が発見された」と常素霞著「中国玉器発展史」の中に書かれている。中国人が書いたものなので、少し眉唾ではあるまいかと当初は疑っていたのだが、何冊かの他の本を読んでみて、どうも本当のようだ。
じつはこう書いている今でも、「玉とはいったい何なのだろう?」との気持ちが自分の心の中にある。広辞苑にはこう書いてある。「たま。宝石。珠(じゅ・貝の中にできる丸い球)に対して美しい石をいう。硬玉・軟玉の併称。白玉・翡翠(ひすい)・黄玉の類」 わかったようで、よくわからない。40年前に私が持った認識は、かならずしも間違っていなかったような気もする。
ただ、玉というものはその言葉からして、貴く、得難く、価値あるものであることはわかる。玉体(ぎょくたい)・玉顔(ぎょくがん)・玉璽(ぎょくじ)・玉音(ぎょくおん)・玉酒(ぎょくしゅ)・玉杯(ぎょくはい)などは、皇帝や天皇に関係する言葉のような気がする。玉砕(ぎょくさい)という言葉からは太平洋戦争を思い浮かべるが、中国の古書「北斉書」の中に見える。玉石混淆(ぎょくせきこんこう)・金科玉条(きんかぎょくじょう)という言葉も中国の古典の中にある。私の文章はいわば「石稿」だが、優れた文章のことを「玉稿」という。すべての言葉に、「すぐれて貴い」という意味が込められているようだ。
切磋琢磨(せっさたくま)という言葉は『詩経』の中にある。当時から現在と同じく、自己研鑽ぶりを表した四文字熟語であるが、本来はそれぞれの文字が、材料を加工する作業を表示しているのだという。「切」は骨を切って加工する作業。「磋」は象牙をといで加工する作業。「琢」は玉(ぎょく)を打って加工する作業。「磨」は石を磨いて加工する作業。このような意味らしい。