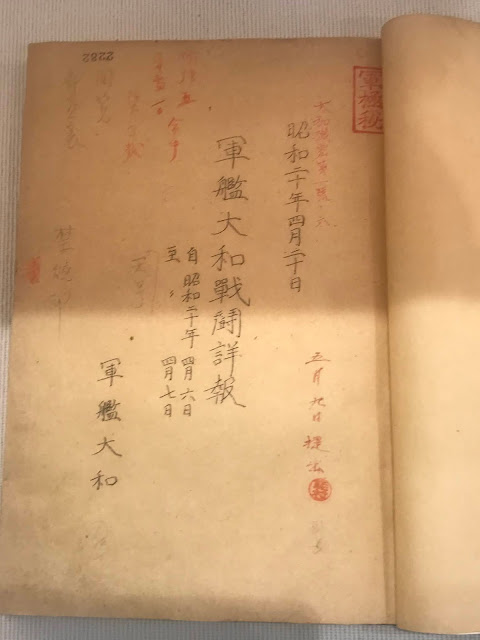"My aunt will be down presently,Mr.Nuttel," said a very self-possessed young lady of fifteen; "in the meantime you must try and put up with me."
Framton Nuttel endeavoured to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately he doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing.
"I know how it will be," his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat; "You will bury yourself down there and not speak to a living soul,and nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, here quite nice."
Framton wondered whether Mrs.Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division.
"Do you know many of the people round here?" asked the niece, when she judged that they had had sufficient silent communion.
"Hardly a soul," said Framton. "My sister was staying here, at the rectory, you know, some four years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here."
He made the last statement in a tone of distinct regret.
"Then you know practically nothing about my aunt?" pursued the self-possessed young lady.
"Only her name and address," admitted the caller. He was wondering whether Mrs.Sappleton was in the married or widowed state. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation.
"Her great tragedy happened just three years ago," said the child; "that would be since your sister's time."
"Her tragedy?" asked Framton; somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place.
"You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon," said the niece, indicating a large French window that opened on to a lawn.
"It is quite warm for the time of the year," said Framton; "but has that window got anything to do with the tragedy?"
"Out through that window, three years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for their day's shooting. They never came back. In crossing the moor to their favourite snipe-shooting ground they were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warming. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it." Here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly human.
"Poor aunt always thinks that they will come back some day, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk.Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing 'Bettie,why do you bound?' as he always did to tease her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still, quite evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window-----"